
| 離婚の基礎知識 | |||
| 1:離婚とは | 2:夫婦関係修復 | 3:男性の離婚 | 4:女性の離婚 |
| 5:離婚の種類 | 6:協議離婚 | 7:調停離婚 | 8:裁判離婚 |
| 9:法定離婚事由 | 10:浮気・不倫 | 11:悪意の遺棄 | 12:その他の事由 |
| 13:婚姻費用 | 14:離婚の慰謝料 | 15:財産分与 | 16:子供の養育費 |
| 17:子供の親権 | 18:面会交流権 | 19:年金分割 | 20:離婚協議書 |
離婚の財産分与とは、婚姻中に夫婦で築きあげた財産の清算・分配のことです。
離婚をした者の一方は、相手方に対して財産分与を請求することが出来ます。
| 民法第768条 | (財産分与) |
| 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 |
財産分与とは、離婚に伴って生じる身分上・財産上の一切の清算ということが目的であるため、以下の4つの要素を含んでいます。
| 1 | 夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産の清算 |
| 2 | 別居時から離婚成立に至るまでの期間における生活費(婚姻費用)の清算 |
| 3 | 離婚後の経済的弱者に対する一定の扶養 |
| 4 | 一方の有責な行為によって他方に与えた精神的苦痛に対する慰謝 |
上記の趣旨により、財産分与は、大きく分けて以下の4種類に分類されます。
(1)清算的財産分与
(2)扶養的財産分与
(3)慰謝料的財産分与
(4)婚姻費用清算の財産分与
清算的財産分与とは、純粋に、夫婦が協力して築きあげた財産を平等に分配することをいいます。
この「清算的財産分与」が原則であり、これを補うものとして、必要に応じて「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」「婚姻費用清算の財産分与」が行われます。
清算的財産分与において、その対象となる財産財産には、共有財産と実質的共有財産とがあり、対象とならない財産として「特有財産」があります。
原則として、婚姻期間中に築き上げた財産は、名義の如何を問わず、どちらに属するか定かでない場合、夫婦の協力によって形成された共有財産と推定されます。
夫婦のいずれか一方が、個人的な才覚によって得た財産や相続によって取得した遺産などは、特有財産とされます。
なお、特有財産であっても、他方がその財産価値の減少防止に協力・貢献をしていたと認められる場合には、一定割合の分与を認められる場合があります。
| 民法第762条 | (夫婦間における財産の帰属) |
| 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 | |
| 2 | 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 |
|
財産分与の対象となる共有財産には、以下のものがあります。
<退職金>
退職金については、2〜3年以内に支給予定で、かつ、支払われる可能性が高いこと、受取人に対する他方の貢献度が大きいこと、などの事情があれば、共有財産として、財産分与の対象となります。
もっとも、分与される時期は退職金が支払われた時、となることが多いようです。
<借金>
不動産や自動車のローン、教育ローンなど、夫婦生活において必要な借金は、マイナスの財産として、それ自体も財産分与の対象です。
<一方の配偶者の経営する会社名義の財産>
原則として、会社名義の財産は、会社固有の財産であり、財産分与の対象とはなりませんが、仮に、その会社が実質的にみて個人経営と変わらないような場合には、財産分与の対象となることがあります。
また、いずれか一方の配偶者の両親の経営する家業ないし個人会社で従事していたというような場合も、実質的には家族全員の共有財産であるとして、婚姻していた期間に応じて財産分与の対象となることがあります。
<特定の資格>
一方の配偶者が、弁護士や医師などの特定の資格を有している場合で、その資格取得のために、他方の配偶者が協力して支えてきたというような特別な事情がある場合、その貢献によって無形の財産を得たものとして、財産分与の対象となることがあります。
特有財産とは、夫婦の一方が婚姻前から持っている財産、および婚姻中に自己の名義で得た財産のことをいいます。
特有財産は、離婚の財産分与の対象にはなりませんので、注意が必要です。
以下のようなものが、特有財産にあたります。
夫婦生活において必要な不動産や自動車のローン以外の借金(債務)は、特有財産(マイナスの財産)となり、財産分与の対象とはなりません。
ただし、他方が連帯保証人となっている場合には、いずれもが同等の責任を負うものであり、離婚しても責任を逃れることは出来ません。
財産分与の対象となる財産は、離婚成立時の財産を基準に計算します。
しかし、離婚前に別居となった場合、通常は、別居時の財産を基準に財産分与の計算を行います。
ただし、別居後にも協力関係があったのであれば離婚成立時の財産が基準となります。
財産分与の割合は、共稼ぎや共同経営する自営の場合には、通常、対等(半々)として計算します。
専業主婦(専業主夫)の場合には、判例上、貢献度に応じて、30%〜50%とされることが多いようですが、最近の傾向としては、専業主婦であっても2分の1が相当だとする判例が増えてきています。
扶養的財産分与とは、「離婚後扶養」などともいいますが、離婚することによっていずれか片方が経済的に窮する場合などに扶養の意味で財産を分与することをいいます。
専業主婦が幼児を抱えているために職に就けない、などの事情がある場合には、夫にはこれを扶養すべき義務があります。
ただし、経済的自立の目処がたつまでの保障であり、経済的に窮する状態にない場合には、この扶養的財産分与は行う必要がありません。
扶養的財産分与の場合には、慰謝料とは異なり、支払総額が確定しないことも許されます。
※例:再婚するまで月10万円づつ支払う
就職が決まるまで月10万円づつ支払う
など。
|
慰謝料的財産分与とは、慰謝料と財産分与の額や割合を定めず、一括して分与することをいいます。
慰謝料の算出が困難な場合などはこの慰謝料的財産分与によって一括して分配・清算を行います。
名目上の如何を問わず、判例上、当事者間の財産分与の額から推測して、慰謝料も含まれていると判断出来る場合には、別途に慰謝料の請求を行うことは出来ないとされています。
婚姻費用清算の財産分与とは、離婚前に別居していて生活費(婚姻費用といいます)を渡してもらえなかったなどという場合に、この生活費(「婚姻費用」)も含めて行う財産分与のことをいいます。
婚姻生活の費用は、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して分担する
(民法第760条)
まず初めに、財産分与すべき「共有財産」を確定し、「特有財産」として除外すべきものと区別します。
そして、現金と預金以外の財産については、評価額を算定し、夫婦双方の取得分・持分割合などを定めます。
具体的な分割方法としては、大きく分けて、現物分割、代償分割、換価分割、等があります。
| (1) | 現物分割 |
| 現物分割とは、そのまま金銭を支払う、不動産や動産(家具・電化製品、自動車等)などの現物を受け取る、という方法のことです。 | |
| (2) | 代償分割 |
| 代償分割とは、例えば、一方が不動産の価額の半額を現金で支払う代わりに不動産の所有権を移転してもらう、等、現実的な分割をしないで対価を支払うという方法のことです。 | |
| (3) | 換価分割 |
| 換価分割とは、例えば自動車を売却するなどして換金し、諸経費を差し引いた残額を分け合う、という方法のことです。 | |
結婚後に購入した不動産で、住宅ローンが残っていないという場合には、売却して得た利益を折半すれば良いですし、売却しない場合には、評価額を折半する方法がとれます。
ただし、住宅ローンが残っている場合には、注意が必要です。
夫婦の一方が連帯保証人または連帯債務者となっている場合、債権者(銀行など)に対しては、離婚をしたとしても、そのまま双方が支払い義務を負います。
連帯保証人または連帯債務者になっていないのであれば、ローンの支払義務はありません。
例えば、ご主人が不動産の所有権の単独名義で、そのまま住み続けるいうことであれば、そのままご主人のみが支払義務を負います。
もしも売却しようとする場合、売却額(評価額)よりローンの残債の方が多いと、そもそも不足分を一括して支払わない限り、抵当権を抹消出来ませんので、売却することが出来ません。
この場合、不足分を埋めて売却をするということであれば、その金額について、折半するというのが合理的です。
原則として、離婚に伴う慰謝料や財産分与に税金はかかりません。
ただし、社会通念上の許容範囲を超えた高額であると判断された場合や、贈与税や相続税を逃れるためと判断された場合には、贈与税が課せられる場合がありますので注意が必要です。
また、不動産の譲渡に関しては、以下のとおり、課税される場合があります。
離婚による財産分与を受けた場合、原則として、贈与税がかかることはありません。
これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦2人で築いた財産の清算や、離婚後の生活保障として財産分与請求権に基づく給付を受けたものと考えられるからです。
ただし、例外的に贈与税がかかる場合が2つあります。
(1)分与された財産が過大であると判断された場合
(2)離婚の目的が贈与税や相続税を逃れるためであると判断された場合
所得税法上、損害賠償金は非課税となり、原則として所得税がかかりません。
ただし、離婚に伴う財産分与として、土地や建物を譲渡する場合、原則として、財産を譲渡する側に、所得税が課税されます。
※所得税法 第33条(譲渡所得)
ただし、居住用不動産(マイホーム)に関しては、離婚成立後に所有権移転の手続きを行うのであれば、所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
※この特例は、親族外への譲渡である場合のみ適用されるため、離婚後に所有権移転の手続きを行う必要があります。
【収入金額−取得費−譲渡費用−特別控除=譲渡所得】
・収入金額とは、財産分与する時点での土地や建物などの時価のことをいいます。
・取得費とは、不動産の購入代金や購入手数料、および、その後に支出した改良費、設備費などの合計です。
・譲渡費用は、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、借家人への立退料、建物の取壊し費用などの合計です。
なお、婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、離婚前であっても、居住用不動産を譲渡される側が引き続き居住するのであれば、贈与税の基礎控除110万円と配偶者控除2,000万円が適用され、総額2,110万円まで非課税となります。
※控除の対象となるのは居住用不動産の場合のみです。投資用不動産や別荘・セカンドハウスなどの不動産は適用されません。
※転勤・別居などでその不動産に住まなくなって3年以上が経過している場合、控除が受けられない場合があります。
将来的に売却処分しようとする場合に、財産分与によって取得した時の価額との差によって、譲渡取得税が生じる場合がありますので、この点も、ご注意下さい。
通常、不動産を取得した側には、不動産取得税が課税されます。
ただし、婚姻後に取得した不動産であって、取得原因が贈与や相続で無い場合、離婚における「夫婦の財産の清算」という名目であれば、非課税ないし軽減される場合があります。
所有権移転の登記を申請する際、固定資産税評価額の2%の登録免許税がかかります。
債務者が、債権者からの差押えを回避するために自己の財産を他に贈与してしまう等の行為を「詐害行為」といい、裁判に訴えることによって取り消すことが出来ます。
ただし、財産分与は「身分行為」とされ、通常の売買などの財産行為とは異なり、原則として、債権者の権利を侵害する行為(詐害行為)とはされません。
しかし、社会通念上の許容範囲を超えた高額な分与である場合には、詐害行為として取り消される可能性はあります。
| 最高裁 昭和58年12月19日判決 |
|---|
|
要旨 離婚に伴う財産分与は、財産分与についての法律の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託された財産処分であると認めるに足りるような特段の事情がない限り、詐害行為とはならない。 |
| 最高裁 平成12年3月9日判決 |
|---|
|
要旨 離婚に伴う財産分与として金銭の給付をする旨の合意は、原則として詐害行為とはならない。しかしながら、民法767条3項の規程の趣旨に反してその額が不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情があるときは、不相当に過大な部分について、その限度において詐害行為として取り消されるべきと解するのが相当である。 |
詐害行為となるかどうかのポイントで重要なのは、以下の2点です。
1.離婚の時期,移転の時期
2.対象となる財産の金額
離婚の財産分与請求権の時効は、離婚が成立してから2年間です。
| 離婚の基礎知識 | |||
| 1:離婚とは | 2:夫婦関係修復 | 3:男性の離婚 | 4:女性の離婚 |
| 5:離婚の種類 | 6:協議離婚 | 7:調停離婚 | 8:裁判離婚 |
| 9:法定離婚事由 | 10:浮気・不倫 | 11:悪意の遺棄 | 12:その他の事由 |
| 13:婚姻費用 | 14:離婚の慰謝料 | 15:財産分与 | 16:子供の養育費 |
| 17:子供の親権 | 18:面会交流権 | 19:年金分割 | 20:離婚協議書 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

私は、幼いころに両親が離婚し、母子家庭で育ちました。 >>>代表者ご挨拶
行政書士 小竹 広光 |

|
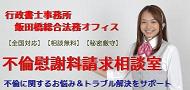
|

